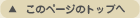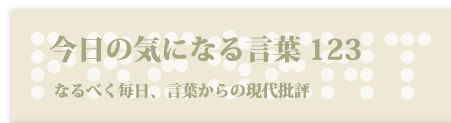
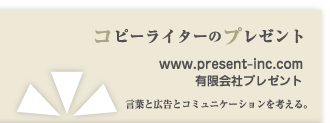
"できる限り毎日更新"を基本にあらゆるメディアで、
あるいは群衆の中で出合った「気になる言葉」をピックアップ。
すべて123文字で綴った日本語論・日本人論である。 |
★123文字による簡潔な情報伝達の文章スタイルは「知的所有権登録
187441号」を取得しています。 |
24年間にわたるバックナンバーはこちらから |
2023年6月12日
|
「毎日更新。」
は結局できなかったが、2000年11月9日から続けてきた「今日の気になる言葉123」を明日から「今週の気になる言葉123」に変更し、WEBサイトを刷新する。足掛け24年、よくやったという自己満足を感じつつ新たなコンテンツにまだまだ挑んでいきたい。
●No.7648/6.12 川中紀行の新しいWEBサイトです。 コピーライターの川中紀行 新たにスタートする「今週の気になる言葉123」はこちらから。 |
「ライムやオレンジのような果実感。」
と「コロンビア ライムハニー(浅煎り)」で使われたフレーズ。近所のカフェのメニューにあったが、さらに「オレンジの皮のような柑橘系由来のスパイシーさ」と書かれると、オレンジの実と皮を区別できない、と思ってしまう。コーヒー豆にもワインと同じ世界がある。
●No.7647/6.11 |
「ノンバイナリー。」
本日初めてネット調査でこの言葉に出合う。身体的性に関係なく自身の性自認・性表現によるセクシュアリティを指す。トイレの性差解放は別問題だが、官公庁の申請で「男」か「女」かしか選択肢がないのを疑問に思っていた。これも自民党の保守的姿勢が影響している。
●No.7646/6.10 |
「生きづらさ。」
について土井裕泰監督は「周囲とうまく同調できない、思い描いたようには生きられない、そんな生きづらさを抱えた人たち」と綴る(先日の『読売新聞』朝刊)。これは私であり多くの人間だ。最近安易に「生きづらい社会」と言うが、より具体的に理由を伝えてほしい。
●No.7645/6.9 |
「明日のことばっか考えてたら、
せっかくのいまが もったいない。」
男装ホストのルイ(鈴木ゆうか)のPRに悩む久美子(桜井ユキ)に、そのルイがかけた言葉(昨日の『ホスト相続しちゃいました』)。マインドフルネスはじめ現在・過去・未来のなかで生き方を変える手段として「いま」に集中する思考法が脚光を浴びてきた気がする。
●No.7644/6.8 |
「本を自分のフィルターを通して渡す人、
紹介する人を 私は書店員と呼んでいる。」
と語ったのは田口幹人氏(先日の『週刊テレビ批評』)。大手チェーン書店と店主独自の視点で本をセレクトする個人書店とに二分化されつつある印象も受けるなかで、この「書店員」という言葉は、書籍に自分の視点をプラスして販売する自営業へと変わるのであろうか。
●No.7643/6.7 |
「その人がどんな人かは、
その人がそれまでの人生で 何を食べてきたかで分かる。」
と金平茂紀氏(『Apron』June)。氏は特に出身地ならではの食材との関連を言うが、食の好みや重視するポイントは長い人生で変わるから、「何を食べてきたか」は、年齢ごとに追跡しないと分からない。冒頭でこう書いたら、そこまで書くべきではなかったか。
●No.7642/6.6 |
「空気だ、空気だ、空気をつくるよ!」
対戦相手の湘南ベルマーレに先制された後、川崎フロンターレのサポーター・コールリーダーを務めるカイト氏はこう叫んだ(先月の『100カメ』)。「空気をつくる」はゴール裏にいると実感する。サポーターの声援が攻勢を後押ししていると感じつつ声援を送るのだ。
●No.7641/6.5 |
「第7の大陸。」
プラスチックが粒子化したゴミが集まった光景をこう伝えた先月の「ワールドニュース/France 2」。総面積はフランスの6倍と報じたが、エベレストでは標高8千mの頂上付近でゴミ収集活動を行う。年間4億6千万tのプラスチック生産量の約8割がゴミになる。
●No.7640/6.4 |
「一歩踏み出す勇気をもってほしい。」
と田中仁・ジンズホールディングス代表取締役CEO(先月の『ワールドビジネスサテライト』)。宿泊費4万円超の「白井屋ホテル」として地元老舗旅館を復興させ出身の前橋の街再生を進める。これは起業家を育成する「群馬イノベーションスクール」の生徒に言った。
●No.7639/6.3 |
「こちらは八丈島のスーパーです。
台風の接近が予想されるなか、 船が欠航した場合に備えて、 今朝の船で3日分の商品を まとめて入荷しました。」
と本日午後0時15分のNHK ニュース。台風2号による影響を報じたが、主語の「スーパー」を活かせば「入荷」を「補充」に変えるか「入庫させ」にするか。ただこの場合、「商品」を主語にして「商品が」とするのが自然だ。プロの書き手にも助詞の過ちが頻発する。
●No.7638/6.2 |
「深酒を避けるために
この一杯を、まっ、舌の裏表、 口じゅうにふくめて、 全ての味を味わって、思い切って、 ぐいっと飲み込む。 すると切れがいいから 後味が残らない。」
先月の「ふらり旅・新 居酒屋百選」の家飲み特集でそう語った太田和彦氏。だから「口の中の(酒の)滞在時間がずっと長くなったのね」と言い「すぐに飲み込んじゃうのがもったいない」とも。私は食事でこれを実践してよく噛み、よく味わって飲み込むようにしている。
●No.7637/6.1 |
川中紀行のnoteもぜひご覧ください。 「今日の気になる言葉123」と一部が連動しています。 |
22年間にわたるバックナンバーはこちらから |